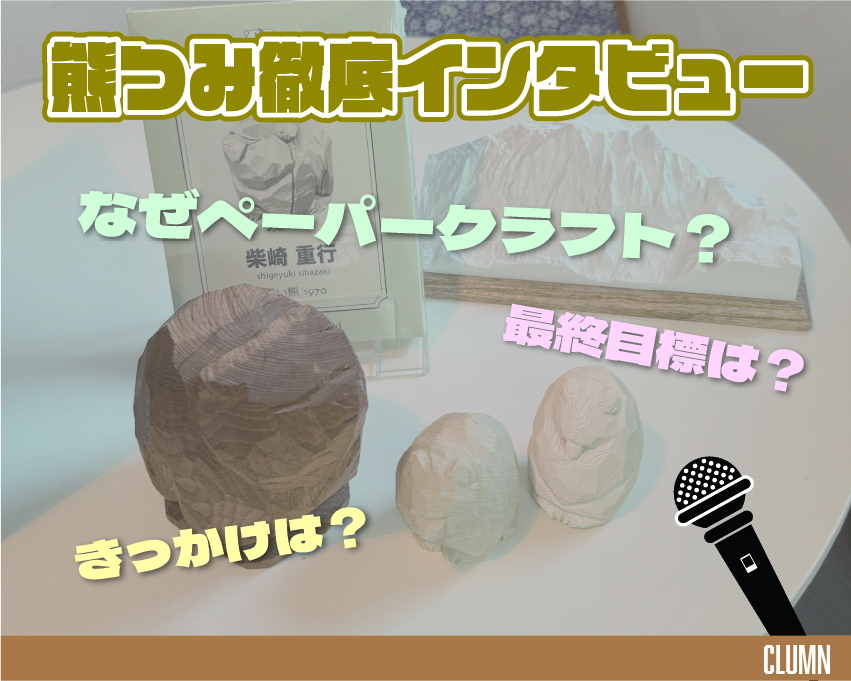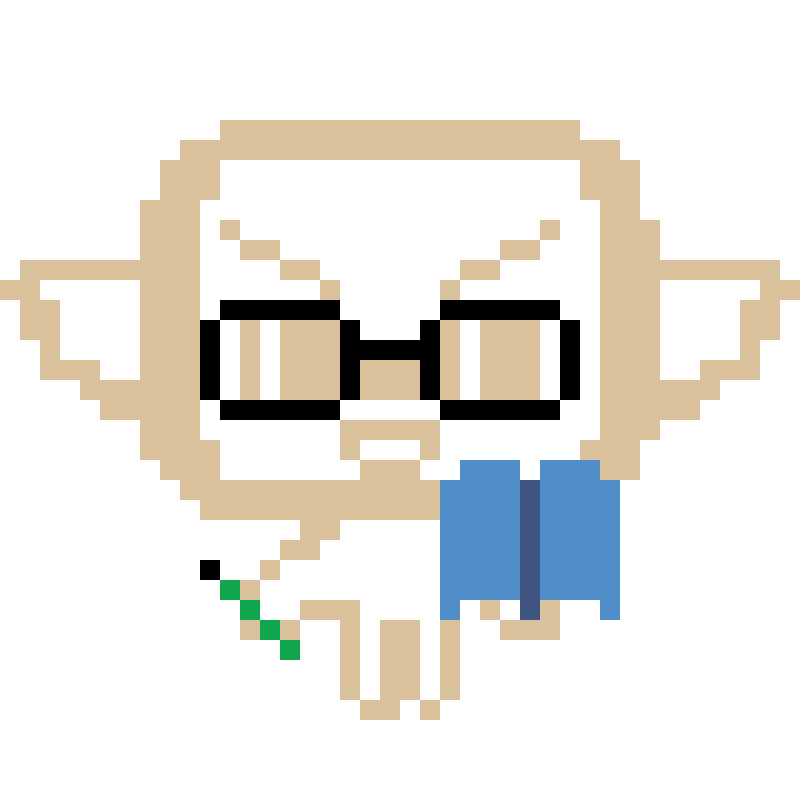
つばナビ君と行く!まちで活躍するキーパーソン「やくも人探訪」vol.2 有限会社高木水産 高木一哉社長、智佳子さん
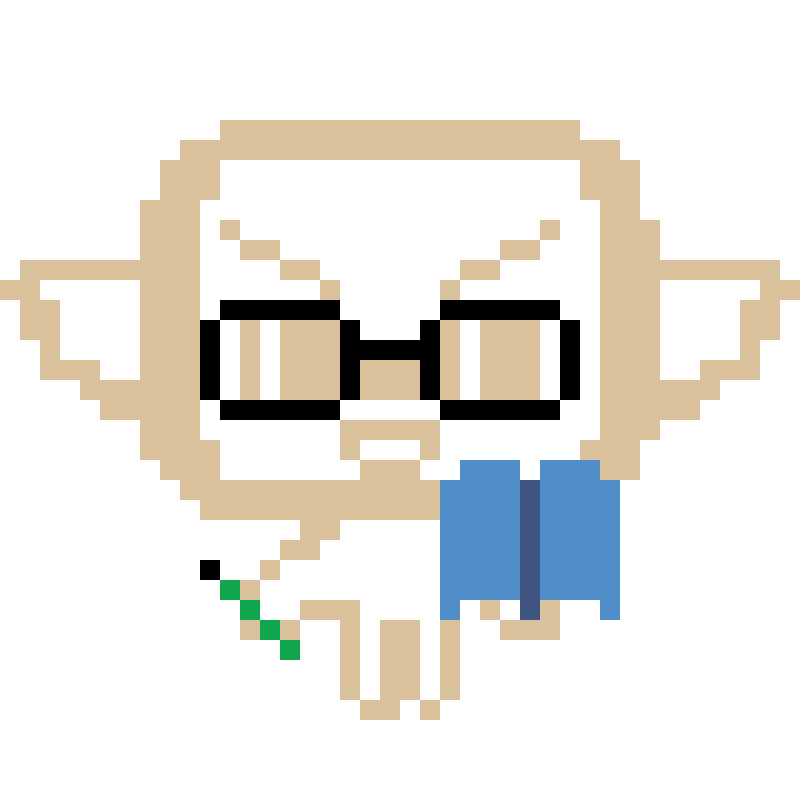

こんにちは!つばナビ君です。
今日は僕がアップした記事「つばナビ君の気になるお店 vol.2 八雲の美味しい魚を届けたい!「高木水産」 」と合わせて取材してきた「つばナビ君と行く!まちで活躍するキーパーソン『やくも人探訪』」の第2弾をお届けします!
(前回の記事もぜひ読んでみてください)
「地元の魚のおいしさを多くの人に広めたい」「ヤマタカ高木水産の高木一哉社長、智佳子さんに聞く
八雲町の水産物をたくさんの人に届けるお仕事。その中のひとつ、地元で長年親しまれている水産加工業者「ヤマタカ高木水産(以下高木水産)」さん。今回は、社長の高木一哉さんと奥様の智佳子さんにお話を聞いてきました。

高校時代から続くセリとの関わり
高木水産は昭和の時代、魚の仲介だけでなく雑貨なども扱う商店でした。
しかし時代の移り変わりとともに魚の取り扱いが中心となり、昭和62年には商店をやめ魚一本に集中する今の形に。一時期は海沿いに工場を移し、約15年間ホタテの加工も手がけていましたが、現在の形になってからおよそ15年になるそうです。
「家を継ぐと決めたのはいつですか?」とお聞きすると、驚くようなお話が返ってきました。
実は高木さんは幼い頃から家業を手伝い、学生時代からすでに魚の買い付けという責任の重い仕事に関わっていたのです。
高校3年生の秋、お父さまが入院したことをきっかけに、長男として代わりに漁港のセリに通うことになりました。
当時は「譜丁(ふちょう)」と呼ばれる符号を使った取引が主流で、とても難しく最初は大きな苦労があったといいます。
それでも朝5時半からホッキのセリに参加してから学校へ登校し、昼で早退して午後のセリに向かう――そんな日々を続けました。
お父さまが退院してからも魚を運ぶ仕事は続き、この経験が今の基盤となっています。
豊漁の日は体力勝負
高木さんと智佳子さんは、高木さんのお姉さまが勤めていた職場に奥さまも勤務していたことがご縁で出会い、その後昭和62年に結婚。以来ずっと、夫婦二人三脚で八雲の海とともに歩んできました。
現在も、漁港で仕入れた魚を高木さんが運び入れ、智佳子さんと二人で素早く選別・仕分けし、箱詰めして出荷しています。ときには思わずたまげるような大漁の日もありますが、智佳子さんは落ち着いて手際よく作業を進め、その存在は高木水産の大きな力となっています。
先日の八雲の山車行列の日の朝には、ヒラメが3枚入りの箱で100箱に。
事前に「30箱でいい」と電話で伝えられ、智佳子さんが氷を入れて準備していたものの、全く足りずに大慌て。と二人で笑い話として語っておられました。
今年の年始にはニシンが豊漁で、一番多い日は1日で500キロを出荷したことも。
取材日にも高木さんが2往復して運ぶ大漁の砂カレイに、智佳子さんは驚くことなく、冷静に魚を選別し、美しく箱詰めしていく姿が印象的でした。


紫の箱は信頼の証
長年きっちりとした仕事を積み重ねてきた結果、市場では「紫の箱なら間違いない」と言われるようになり、高木水産の発泡スチロールに印刷された紫のロゴは、いまや品質の象徴になってきているらしいと高木さんはおっしゃいます。
「中身は同じ魚でも、箱に傷がついていたり外見が悪いだけで値段に響くんです。だからその辺も気を遣わなければならない。バンドをしっかり締めるための専用の機械もあるんだよ」と高木さん。
見えないところにまで細やかな心配りがあるからこそ、信頼は築かれているのだと感じさせられました。

八雲の魚のポテンシャルを伝えたい
「八雲の魚は本当にポテンシャルが高いんです」と高木さん。
見た目が不格好で市場で注目されにくいカガミダイも、自分たちで食べて「これは旨い」と確信すれば、食べやすいように加工して提供します。
するとお客さまから「美味しい!」と驚かれ、やがて繰り返し食べてくれるように。
「一回だまされたと思って食べてみてよ、とすすめると、結局ファンになってくれるんです」と笑顔を見せます。
漁港で仕入れた魚は、生のまま市場へ出荷するものと、冷凍して加工するものに分けられます。
冷凍した魚は年間を通じて加工され、鮭とば・鮭の半身などの人気商品に。
特に鮭とばは食感が抜群の“半生”で仕上げるのが高木水産流。半生でありながら保存料などを使用しないので冷凍流通でなければ販売が難しく外販の依頼も受けづらくなかなか広まりにくいのですが、それでも「本当に美味しい」とリピーターが多い逸品です。
「塩加減や味のレシピは、自分で繰り返して作り出してきたもの。自信があります」と高木さん。「『やっぱり高木さんの味だね』と言ってもらえたことがあって、本当に嬉しかった」と振り返る高木さん。
魚を洗う時間や塩をする時間も魚ごとにきちんと決め、徹底して守る。日々の積み重ねが、味そのもので信頼を築いているのです。

今が一番面白い
高木さんは噴火湾の魚の魅力をいかに引き出し、多くの人に伝えるかを常に考えています。
「挑戦したいことは特にない。今あることをしっかりやっていくだけ」と語る姿には、積み重ねてきた経験から生まれる揺るぎない自信がありました。
「昔と比べると、水揚げされる魚の種類や時期もだいぶ変わってきた」と高木さん。気候や海の変化もあり、漁のスケジュールは年々読みづらくなっています。そのなかで、今ある環境をうまく活かしながら魚を届け続けることが課題です。
そして最後に、こんな言葉を聞かせてくれました。
「机に向かってカリカリやるタイプじゃないんです。今が仕事していて一番面白い。」
魚の可能性を広げ、八雲の海の魅力を届ける毎日は、苦労もあるけれどやりがいにあふれています。

つばナビ君の編集後記
今回の取材は、実は全部で4回にわたりました。
最初に4月の頭に伺ったときはちょうど魚がない時間にいき、お話を聞くだけでしたが、その熱意に触れ「これは実際に現場を見なければ伝えきれない」と強く感じました。
特別に八雲漁港でのセリと出荷の様子を取材させていただき、大漁の砂カレイを2往復して運ぶ高木さんと、冷静に美しく箱詰めしていく智佳子さんの姿を目にしました。
その後「高木水産さんのお店紹介」の記事を公開(https://tsubanavi.com/food/911/)。
ご夫婦の姿を撮影させていいただきたいと追加取材に伺ったものの、なんとカメラにメモリーカードが入っていないという痛恨のミス!
結局、記事を書いたあとにもう一度お願いして再撮影させていただきました。
加工場に並んでいたたくさんのポットも印象的でした。最初は「お茶をたくさん飲むのかな」と思ったら、寒い時期に手を温めるためのお湯だったのです。
冬の厳しさを乗り越える知恵に驚かされました。

4回の取材を通して強く感じたのは、八雲の魚のポテンシャルの高さ、そしてご夫婦のこだわりと誠実さ。
市場では「紫の箱」で信頼され、味付けでも覚えられる。表に出ることは少なくても、確かな仕事ぶりが人に伝わり、八雲の魚の価値を広げています。
もっと多くの人に、この町の魚の魅力と、高木水産の挑戦が知られていくことを願っています。